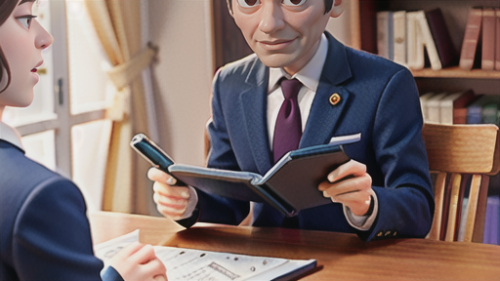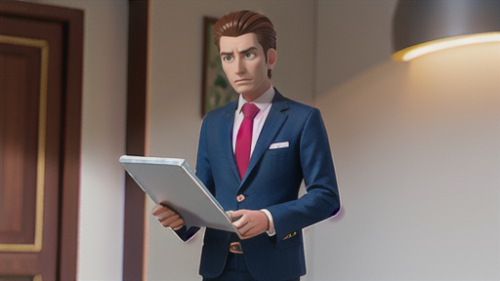転職用語
転職用語 転職とリスキリング:均等法の理解
仕事の世界で、男性と女性が同じように扱われるようにするための法律があります。これは「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」という長い名前ですが、普段は「男女雇用機会均等法」または「均等法」と短く呼ばれています。
この法律は、会社で働く際に性別によって差別されないようにするためのものです。会社の仕事には色々な種類がありますが、例えば、人を採用する、仕事の内容を決める、昇進させる、研修を受けさせる、退職してもらうなど、仕事に関わる全ての手続きで男女が平等に扱われなければなりません。簡単に言うと、男性だから、あるいは女性だからという理由で、不公平な扱いを受けてはいけないということです。
例えば、男性だから採用する、女性だから昇進させないというのは、明らかにこの法律に違反します。また、求人票に「男性のみ」「女性のみ」と書くことも禁止されています。性別によって仕事の機会が奪われることがないように、募集の段階から性別で制限を設けてはいけないのです。
妊娠や出産、育児なども、女性にとって仕事をする上で大きな影響を与える出来事です。均等法は、これらの理由で女性が不利益を被らないように守っています。例えば、妊娠を理由に解雇することは違法です。また、育児休業などの制度を利用しやすいように、会社は働きやすい環境を作る努力をしなければなりません。
この法律のおかげで、多くの女性が様々な職種で活躍できるようになりました。しかし、男女の待遇の差や、無意識の偏見など、まだ課題は残っています。より良い社会を作るためには、この法律の意義を理解し、一人ひとりが意識して行動することが大切です。