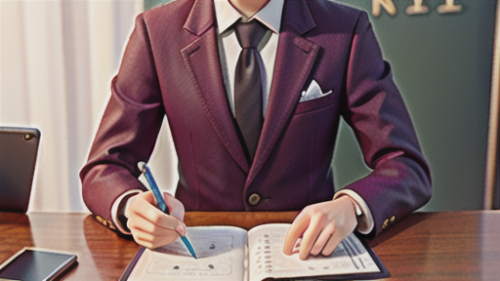転職用語
転職用語 転職とリスキリング:一般常識テストを考える
広く知れ渡っている知識や情報について問う試験を一般常識テストと言います。この試験は、会社が新しい人材を選ぶ際に、応募してきた人たちの基礎的な学力や社会に対する理解度を測るために、しばしば使われています。
試験の内容は様々で、国語、数学、英語といった基本的な教科に加えて、政治、経済、歴史、地理、科学技術、最近話題になっている出来事など、幅広い分野から問題が出されます。
近頃では、インターネットや携帯電話の普及によって、誰でも簡単に情報を得られるようになりました。そのため、単に知識の量が多いだけでなく、得られた情報をきちんと理解し、うまく活用できる能力がより重視されるようになっています。
このような流れを受けて、一般常識テストの内容も変わりつつあります。以前は知識の量を重視する傾向が強かったのですが、最近は思考力や判断力を問う問題が増え、実社会でどれだけ応用できるかを評価する傾向が強まっています。
例えば、時事問題であれば、ただニュースの内容を覚えているだけでなく、その出来事が社会にどのような影響を与えるのか、自分はどう考えるのかといった点を問われることがあります。また、複数の資料を読み解き、論理的に結論を導き出す問題や、グラフや図表から情報を読み取り、分析する問題なども出題されるようになっています。
つまり、現代社会で求められる一般常識とは、単なる知識の詰め込みではなく、情報を活用して問題を解決する能力や、物事を多角的に捉え、論理的に考える力と言えるでしょう。そのため、一般常識テストに向けて勉強する際には、ただ暗記するだけでなく、様々な情報を結びつけて考えたり、自分の意見を持つように心がけることが大切です。