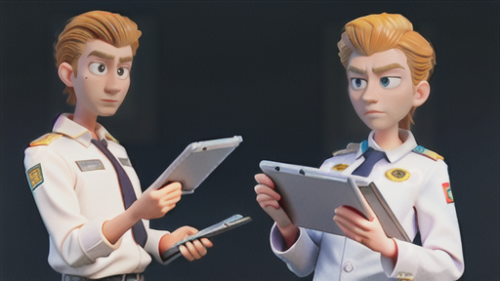IT
IT アプリ開発者のキャリアパスを探る
応用技術者、いわゆるアプリ開発の仕事は、様々な機械や道具を動かすための指示を出す手順、つまりプログラムを作る仕事です。具体的には、携帯電話やパソコンで動くアプリを作るのが主な仕事です。お客さんの「こんなアプリが欲しい」という要望を聞き、それを実現するために必要な手順を考え、実際にプログラムとして作り上げていきます。
アプリを作るには、様々な知識や技術が必要です。まず、プログラムを書くための言葉、いわゆるプログラミング言語を知らなければなりません。色々なプログラミング言語があり、それぞれ得意な分野や特徴があるので、目的に合った言語を選んで使います。また、アプリが扱うデータを保存したり、読み出したりするためのデータベースの仕組みについても理解している必要があります。加えて、アプリを動かすための機器同士をつなぐ通信網、いわゆるネットワークの知識も重要です。最近では、アプリの安全を守るための知識も欠かせません。悪意のある攻撃からアプリやデータを守るための対策を考え、プログラムに組み込む必要があります。
お客さんとの話し合いも大切な仕事の一つです。お客さんの要望を丁寧に聞き取り、それを実現するためにどのような技術が必要なのか、どれくらいの時間や費用がかかるのかなどを説明します。技術的な専門用語を使わずに、お客さんに分かりやすく説明する能力も必要です。また、お客さんの要望が技術的に難しい場合、別の方法を提案することもあります。
アプリが完成したら終わりではありません。作ったアプリを実際に動かしてみて、正しく動作するかを確認する試験、いわゆるテストも行います。もし、アプリに不具合が見つかった場合は、その原因を探し、修正する作業、いわゆるデバッグを行います。アプリを公開した後も、利用者の意見を聞きながら、改善していく作業、いわゆる保守運用も大切な仕事です。このように、応用技術者の仕事は、アプリの企画から開発、公開後の保守運用まで、アプリの誕生から成長まで全てに関わる、幅広い知識と経験が求められるやりがいのある仕事と言えるでしょう。