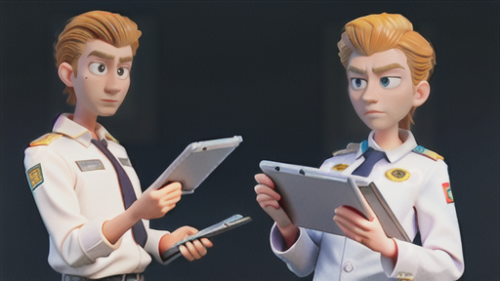医療・福祉
医療・福祉 介護支援専門員:寄り添う専門職への道
介護支援専門員、通称ケアマネージャーは、高齢者や障がいのある方が、自分らしく暮らし続けるためのお手伝いをする専門家です。主な仕事は、介護が必要と認められた方のために、どのようなサービスを利用するかをまとめた「ケアプラン」を作成することです。
ケアプランを作る際には、利用者本人やご家族のお話をじっくり伺います。どのような暮らしを望んでいるのか、現在の生活状況はどうなのか、体の状態や心の状態はどうなのかなど、様々なことを丁寧に尋ねます。そして、その方に最適なサービスを組み合わせて、ケアプランを作成します。
例えば、自宅で生活するための支援が必要な方には、訪問介護や訪問入浴、デイサービスといったサービスを組み合わせることもあります。施設への入所を希望する方には、適切な施設を紹介し、入所手続きの支援も行います。
ケアプランの作成だけでなく、様々な事業者との連絡調整も大切な仕事です。ヘルパーさんや看護師さん、理学療法士さんなど、多くの専門家と連携を取りながら、サービスがスムーズに提供されるように調整します。また、サービスの提供状況を定期的に確認し、状況に応じてケアプランの内容を見直すこともあります。利用者の状態が変化した場合や、新たなニーズが生じた場合は、すぐに対応できるよう、常に気を配る必要があります。
ケアマネージャーは、利用者本人やご家族だけでなく、サービスを提供する事業者、市町村の窓口、病院や診療所など、様々な関係者と連携を取りながら仕事を進めます。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域社会を支える重要な役割を担っているのです。