流動資産と固定資産:正常営業循環基準を理解する

転職の質問
先生、「正常営業循環基準」って資産とか負債を流動と固定に分けるときに使うって聞きましたけど、転職やリスキリングと何か関係あるんですか?

転職研究家
いい質問だね。直接的な関係は薄いけど、会社がリスキリングに投資する場合、その費用が「資産」として扱われるかがポイントになるんだ。ここで「正常営業循環基準」が登場する。

転職の質問
どういうことですか?

転職研究家
例えば、リスキリングで従業員のスキルアップを図ることで、すぐに利益につながる短期的なものなら、一年以内に回収できる見込みが高いから「流動資産」に分類される。逆に、将来の事業展開を見据えた長期的なリスキリング投資は、回収に一年以上かかるから「固定資産」になる。このように、企業の財務状況を分析する際に、リスキリング投資が短期的なものか長期的なものかを判断するのに役立つんだ。
正常営業循環基準とは。
仕事を変えることや、新しい技術を身につけることに関わる言葉で、『いつも通りの営業でのやり取りで見込めるお金の流れ方を基準としたもの』(会社が持っているお金や、会社が払うべきお金を、すぐに使えるものかそうでないかで分ける時に使う基準。普段の商売の中で、一年以内にお金に変わったり、支払ったりするものを見分けやすいお金として扱う方法。この方法と、一年以内かどうかを基準とした方法を両方使って、すぐに使えるお金かそうでないかを分けています。)について。
正常営業循環基準とは

会社の財務状態を示す書類では、資産と負債を、すぐに現金になるか、一年以内に使われるものと、一年以上使われるものに分けています。これは、会社の短期的な支払い能力と長期的な安定性を評価するためにとても大切です。すぐに現金になる、または一年以内に使われる資産を流動資産と言い、一年以上使われる資産を固定資産と言います。この分け方に使われる基準の一つに、正常営業循環基準というものがあります。これは会社の通常の商売の流れの中で、商品を仕入れて、売って、お金を回収するまでの期間を基準にしています。
例えば、ある会社が材料を仕入れて製品を作り、それを販売してお金を受け取るまでの期間が6ヶ月だとします。この期間が、その会社の正常営業循環です。この会社では、たとえ一年以上かかる見込みの棚卸資産があったとしても、それが正常営業循環の6ヶ月以内であれば、流動資産として扱われます。これは、一年という期間だけで判断するよりも、会社の実際の商売の流れを反映した、より正確な財務状況の把握ができるからです。
一年基準と正常営業循環基準は、どちらか長い方の期間が採用されます。例えば、正常営業循環が18ヶ月で一年基準よりも長い場合は、18ヶ月が流動資産と流動負債の判定基準になります。反対に、正常営業循環が8ヶ月で一年基準よりも短い場合は、一年基準が採用され、一年以内に現金化または使用が見込まれる資産や負債が、流動資産や流動負債として計上されます。このように、二つの基準を組み合わせて使うことで、より実態に合った会社の財務状況を理解することができるのです。これは、投資家や金融機関が会社の財務状態を評価する上で、重要な情報となります。
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 流動資産/固定資産の分類 | 1年基準と正常営業循環基準のうち、長い方が採用される | – |
| 1年基準 | 1年以内に現金化または使用が見込まれるもの | – |
| 正常営業循環基準 | 会社の通常の商売の流れの中で、商品を仕入れて、売って、お金を回収するまでの期間を基準とする | 材料仕入→製品製造→販売→代金回収まで6ヶ月 |
| 正常営業循環基準のメリット | 会社の商売の流れを反映し、財務状況をより正確に把握できる | 6ヶ月以内の棚卸資産は、1年以上かかる見込みでも流動資産として扱われる |
| 基準の適用例 | 正常営業循環18ヶ月:18ヶ月基準 正常営業循環8ヶ月:1年基準 |
– |
一年基準との関係
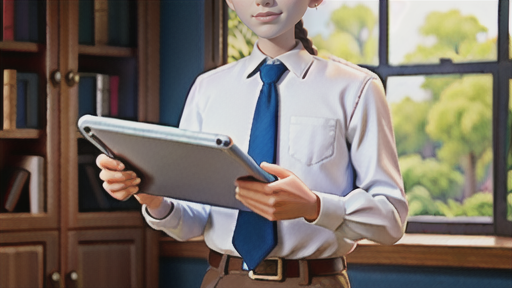
会計の世界では、企業のお金の流れを正しく把握するために、資産や負債を「流動」と「固定」に分類します。この分類において重要な役割を果たすのが一年基準と正常営業循環基準です。
一年基準とは、資産や負債がお金に変わったり、支払いが完了したりするまでの期間が一年以内かどうかを判断基準とするものです。一年以内に現金化や支払いが完了するものは流動、一年以上かかるものは固定に分類されます。例えば、売掛金や仕入債務など、日常的な商取引で発生する資産や負債は一年以内に現金化または支払いが完了するため、通常は流動資産や流動負債に分類されます。
しかし、すべての企業が一年という期間で事業を完結できるとは限りません。そこで、正常営業循環基準という考え方も用いられます。正常営業循環とは、仕入れた商品が売れて現金として回収されるまでの期間のことです。製造業のように、原材料の購入から製品の販売、そして代金回収まである程度の期間を要する業種では、一年基準よりも正常営業循環基準を用いる方が実態に即した分類を行うことができます。
重要なのは、一年基準と正常営業循環基準はどちらか一方を使うのではなく、必ず組み合わせて使うということです。具体的には、一年基準と正常営業循環基準のうち、期間の長い方が流動資産や流動負債を判断する基準となります。例えば、正常営業循環が一年の会社であれば一年基準と同じですが、一年半の会社であれば一年半が基準となります。一年半以内に現金化または支払いが完了するものは流動、それ以上かかるものは固定に分類されます。
このように、二つの基準を使い分けることで、企業の事業活動の実情をより正確に反映した財務諸表を作成することができ、企業の財務状態をより正しく評価することに役立ちます。
製造業における具体例

ものを作る仕事では、材料を買い、製品を作り、売って現金を得るまでにある程度の時間がかかります。この期間の長さを理解することは、会社の状態を正しく把握する上でとても大切です。会計では、一年以内に現金になるものを流動資産としていますが、ものを作る仕事では、仕事の進み具合に合わせて、一年よりも短い期間で現金になるものを流動資産とする場合があります。これを正常営業循環基準といいます。
例として、ある会社で考えてみましょう。この会社では、材料を買ってから製品を売って現金を得るまで、9ヶ月かかるとします。この会社は、一年以内に現金になるものを流動資産として計上することもできますが、正常営業循環基準を使うと、9ヶ月以内に現金になるものだけを流動資産として計上します。つまり、一年基準よりも短い9ヶ月基準を使うため、流動資産として計上するものの範囲は狭くなります。
もし、この会社で材料を買ってから製品を売って現金を得るまで、15ヶ月かかるとしたらどうでしょうか。この場合、一年基準よりも正常営業循環基準の方が長くなります。そのため、15ヶ月以内に現金になるものを流動資産として計上することになり、一年基準よりも流動資産の範囲は広くなります。
このように、正常営業循環基準を使うことで、ものを作る仕事のように、時間がかかる仕事の財務状態をより正確に理解することができます。一年基準だけでは、会社の状態を正しく捉えられない場合があるため、正常営業循環基準は、ものを作る仕事の会社にとって、とても重要な基準と言えるでしょう。
| 基準 | 期間 | 流動資産の範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 一年基準 | 1年 | 1年以内に現金になるもの | 会計の一般的な基準 |
| 正常営業循環基準(例1) | 9ヶ月 | 9ヶ月以内に現金になるもの | 一年基準より狭い範囲 |
| 正常営業循環基準(例2) | 15ヶ月 | 15ヶ月以内に現金になるもの | 一年基準より広い範囲 |
小売業における具体例

小売りの仕事は、商品を仕入れて、お客さまに販売し、お金をいただくという流れです。この一連の流れを商売の周期と考えますと、小売りの場合はこの周期が短いという特徴があります。例えば、お菓子や日用品を扱うお店を考えてみましょう。お店はまずメーカーや卸売業者から商品を仕入れます。仕入れた商品はすぐに店頭に並べられ、お客さまに購入されます。そして、お客さまから代金をいただき、お店は売上を得ます。 このように、商品がお店に届いてからお金に変わるまでにかかる期間は、製造業などに比べて短くなっています。
会計の世界では、この商売の周期を「正常営業循環」と呼び、企業のお金の流れを理解する上で重要な指標となっています。正常営業循環は、会社の財務状態を正しく把握するために使われます。特に、会社の資産を「すぐに現金に変わるもの(流動資産)」と「すぐには現金にならないもの(固定資産)」に分類する際に、この正常営業循環が基準となる場合があります。
例えば、ある小売店の正常営業循環が3ヶ月だとします。1年間を基準とするよりも、3ヶ月という正常営業循環を基準とした方が、お店の実際のお金の流れをより正確に反映できます。1年間を基準とした場合、1年以内にお金に変わるものは全て流動資産とされますが、正常営業循環を基準とする場合は3ヶ月以内にお金に変わるものだけが流動資産となります。つまり、正常営業循環を基準とする方が、流動資産の範囲は狭くなります。
このように、小売りのように商売の周期が短い会社では、正常営業循環を基準とすることで、より実態に合った財務状態を把握することができます。これにより、会社の経営状況をより正確に理解し、適切な経営判断を行うことが可能になります。 小売業だけでなく、飲食業やサービス業など、商売の周期が短い業種では、正常営業循環を意識することが重要です。
財務分析における重要性

お金の流れを正しくつかむことは、会社をきちんと評価するためにとても大切です。そのためには、財務分析が欠かせません。財務分析の中でも、会社の普段の商売の流れに合わせた基準(正常営業循環基準)はとても大切な役割を担います。
会社の財産には、すぐに現金に換えられるもの(流動資産)と、建物や機械のようにすぐには現金に換えられないもの(固定資産)があります。これらの財産を正しく見分けることは、会社の短期的な支払い能力や長期的な財務の健全性を評価する上で、なくてはならないものです。
例えば、会社の短期的な支払い能力を測る指標として、流動比率や当座比率といったものがあります。これらの指標は、すぐに現金に換えられる財産の額に基づいて計算されます。つまり、これらの指標は、会社が短期的な借金を返す力があるかを測るものであり、会社にお金を貸す人や投資をする人にとって、とても大切な情報です。会社の普段の商売の流れに合わせた基準を使うことで、より正確にすぐに現金に換えられる財産の額を把握できるため、財務分析の正確さも上がります。
また、すぐには現金に換えられない財産の額は、会社が長期的にどれだけの規模で商売を続けられるか、また、将来どれくらい利益をあげられるかを評価する上で大切な要素となります。会社の普段の商売の流れに合わせた基準を使うことで、すぐには現金に換えられない財産の額もより正確に把握できるため、会社の長期的な財務状況をより正しく評価することができます。このように、財務分析において、会社の普段の商売の流れに合わせた基準を適用することは、会社の短期的な支払い能力と長期的な財務の健全性をより正確に評価するために、とても重要です。
| 財務分析の視点 | 重要性 | 会社の商売の流れに合わせた基準の役割 |
|---|---|---|
| 短期的な支払い能力 | 会社が短期的な借金を返す力があるかを測る。
|
すぐに現金に換えられる財産の額をより正確に把握できるため、財務分析の正確さが向上する。 |
| 長期的な財務の健全性 | 会社が長期的にどれだけの規模で商売を続けられるか、将来どれくらい利益をあげられるかを評価する。 | すぐには現金に換えられない財産の額もより正確に把握できるため、会社の長期的な財務状況をより正しく評価できる。 |
まとめ

{「まとめ」として、企業活動を適切に評価するための重要な視点である正常営業循環基準について解説します。この基準は、企業のお金の流れ、つまり資産と負債がどのように動いているのかを掴むための重要な考え方です。具体的には、財務諸表、つまり企業のお金の状態を表す書類において、資産と負債を「流動」と「固定」に分類する際に用いられます。
流動資産とは、一年以内に現金化できる、もしくは一年以内に支払いに使われる資産のことで、例えば現金や売掛金、棚卸商品などが挙げられます。一方、固定資産とは、一年以上保有される資産で、例えば建物や機械などが該当します。負債も同様に、一年以内に支払う必要がある負債は流動負債、一年以上かけて支払う負債は固定負債に分類されます。
この分類をする際に、単に一年という期間だけで判断するのではなく、正常営業循環基準も考慮することが重要です。正常営業循環とは、仕入れから販売、そして代金回収までの一連の流れのことです。この循環が一年を超える場合でも、その循環期間を基準として資産や負債を分類するのが、正常営業循環基準です。
例えば、製造期間が長く、製品が完成して販売、代金回収まで一年以上かかる企業があるとします。この場合、一年基準だけで判断すると、製造途中の製品や完成品は固定資産に分類されてしまいます。しかし、正常営業循環基準を適用すれば、これらの資産は一年以内に現金化される見込みがあるため、流動資産に分類されます。
このように、正常営業循環基準と一年基準を併用することで、企業の事業活動の実態をより正確に反映した財務状況を把握できます。これは、財務分析の精度向上に繋がり、企業の短期的な支払能力、つまりすぐに支払いができるかどうかの能力や、長期的な財務の健全性、つまり長く安定して経営できるかどうかの状態をより適切に評価することに繋がります。企業の財務状況を正しく理解するためには、正常営業循環基準の理解が不可欠と言えるでしょう。
| 基準 | 期間 | 資産の例 | 負債の例 |
|---|---|---|---|
| 一年基準 | 1年以内 | 現金、売掛金、棚卸資産 | 買掛金、短期借入金 |
| 正常営業循環基準 | 正常営業循環期間(1年を超える場合もあり) | 製造途中の製品、完成品(製造期間が長い場合) | 長期借入金の一部(営業循環期間に対応する部分) |
正常営業循環:仕入→販売→代金回収までの一連の流れ
正常営業循環基準と一年基準を併用することで、企業の事業活動の実態をより正確に反映した財務状況を把握できる
